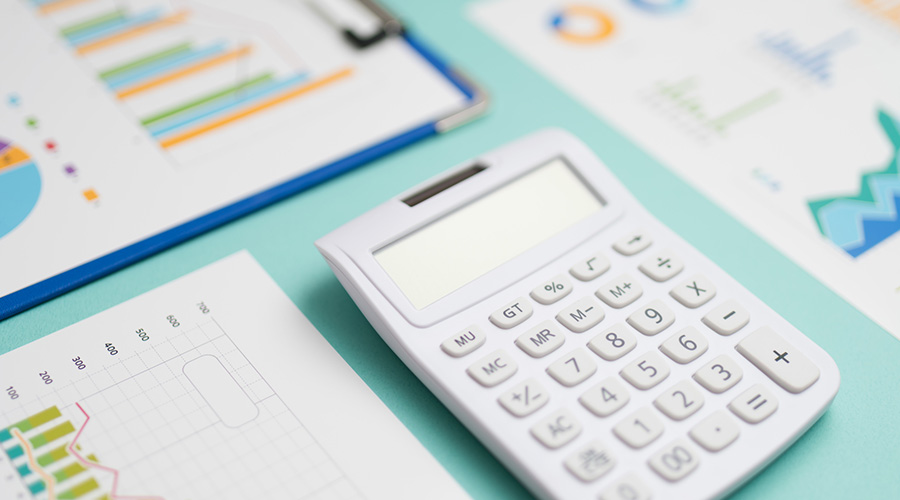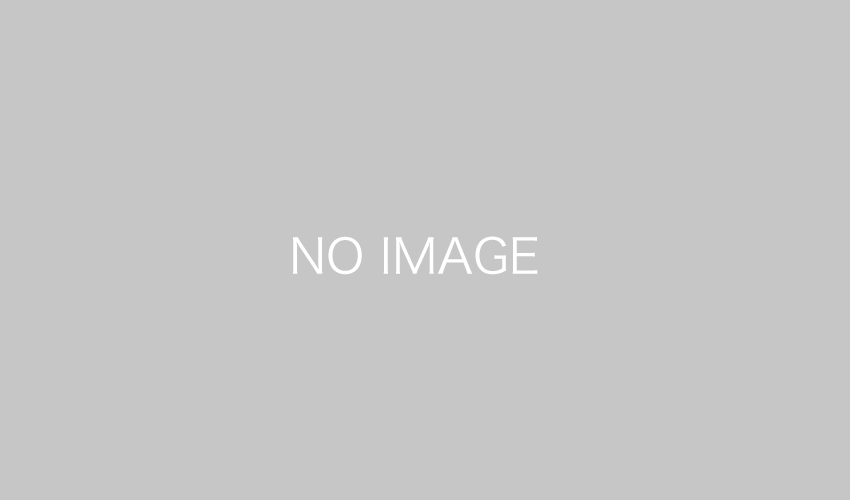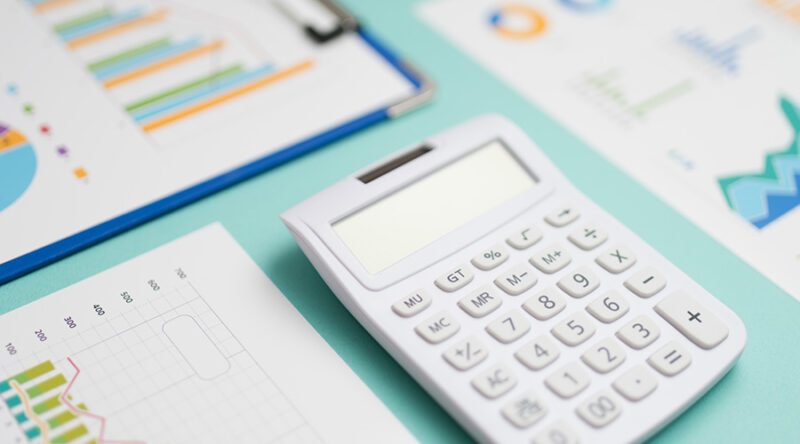【税務職員向け連載2/3】勤務税理士になる前に考えてほしいこと
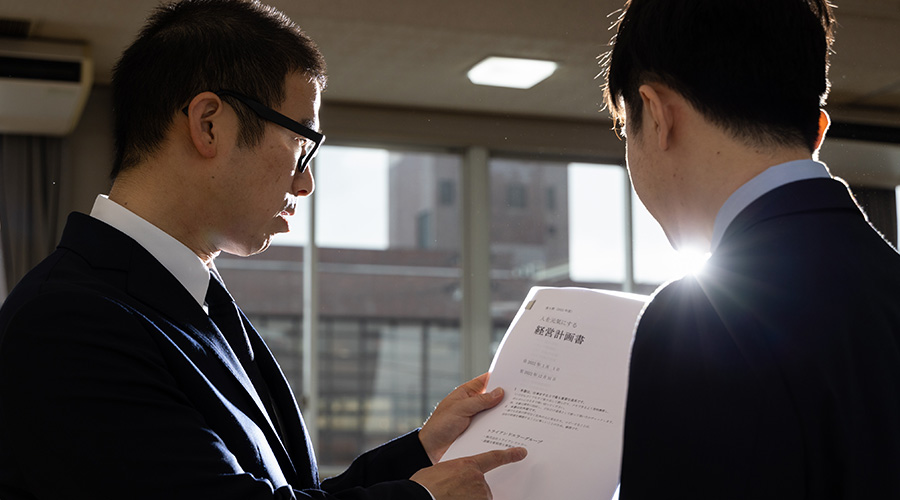
「安定」と「自由」のあいだで揺れるあなたへ
こんにちは。福島県郡山市で税理士事務所を運営している、税理士の遠藤光寛です。
私は国税に18年間勤務し、現在は独立開業して7年目になります。
仙台国税局採用、期別は普通科60期になります。
この連載は、今まさに進路を迷う税務職員の方、特に 「独立するか」 「勤務税理士になるか」 「このまま役所に残るか」 を検討している方に向けて書いています。
前回は「独立税理士になる前に考えてほしいこと」をテーマに、私の実体験と共に、独立開業のリアルをお伝えしました。
今回は第2回。 テーマは「勤務税理士になる前に考えてほしいこと」です。
安定を求めて、あるいは独立のリスクを避けて──税理士法人や会計事務所への就職・転職を選ぶ方も多いでしょう。むしろこちらの方が多数派かもしれません。
ですが、そこで待っている現実もまた、「税務署とはまったく違う」ものです。
1 「知識」より「実務」が問われる世界
国税職員として長年勤めてきた方ほど、税法や調査の知識には自信があると思います。
しかし民間の会計事務所では、その知識がすぐに役立つとは限りません。
たとえば──
- 会計ソフトの入力ができるか
- 電子申告の手続きがスムーズに行えるか
- 顧問先や所員と柔らかくコミュニケーションが取れるか
こうした実務スキルのほうが、はるかに重要視されます。
言い換えれば、 「口だけではなく、手を動かせる人」こそが評価される世界なのです。
2 評価の軸が180度違う
国税では「調査件数」や「役職」が評価の軸でした。 そしてなにより、不正を許さない正義執行という錦の御旗があります。
ですが民間では、「顧問先との信頼関係」や「売上」が評価の中心になります。
正義とは、お客様、事務所の評価です。
不正を暴くことや原則に基づく手続きは劣後します。
つまり── 「業務の正確性」よりも「お客様が継続してくれるか」が重視されるのです。
ここを割り切れない方は、民間の現場で苦しむことになります。
3 自分が一番下
私が知る限りでも、国税を辞めて税理士事務所に勤務すれば、上司が年下(1~2周り)というケースは珍しくありません。
税金に関しては多少の理解があっても、それ以外はほぼ素人。
上下関係の常識が通じない世界です。
プライドの高い元職員ほど、精神的に堪える環境でしょう。
「前の職場では〜」 「国税時代は〜」 ──この言葉は、最も嫌がられるもののひとつです。
4 自分の名前では仕事が来ない
勤務税理士とは、「他人の看板のもとで働く」ということ。
顧問契約は事務所名義であり、あなた個人ではありません。
いくら頑張っても、「自分のファン」はできにくいのが実情です。
また、税理士会やOB会などの会合に顔を出した時も、 勤務(雇われ税理士)と独立税理士の間に、隔たりのようなものを感じることになるかもしれません。
そのことに、ある種の虚しさを感じる人もいるかもしれません。
5 「ボーナス」と「自由」は両立しない
勤務税理士には、開業税理士にはないメリットがあります。
- 固定給+賞与(あれば)
- 社会保険・雇用保険
- オフィスや消耗品は事務所が用意してくれる
これは、家庭や安定を優先したい方にとって、大きな安心材料でしょう。
ただし──
- 自分の裁量で仕事を設計したい
- 顧問先を選びたい
- 方針に納得できないと動きたくない
といった希望は、多くの場合、叶いません。
たとえるなら── 給与という名の“安定した舟”に乗る代わりに、舵(かじ)を握ることはできない、というイメージです。
たとえ税務のプロとして正しい判断ができたとしても、 組織の決定には従わなければならない場面もあるでしょう。
そのたびに、これまでの価値観をねじ曲げられるような感覚に、苦しさを覚える人もいます。
6 腰掛け扱いされることもある
新しい職場に入ったら、当然ながら「新人」としてのふるまいが求められます。
職場はコミュニケーションで成り立っており、周囲と柔軟にやっていくことは必須のスキルです。
とくに、周囲の空気を破壊するのは開口一番のこの一言。
「新人に戻ったつもりで~」 戻ったつもりじゃなくて、新人です。
事務所職員はあなたがどんな人間か値踏みしています。
こんなずれた発言をするようなら、その後の評価は決まったと言っても過言ではありません。
「税理士資格を持った1年生」── それが、職場のあなたに対する認識です。
- タメ口は御法度
- 事務員がやるだろうという態度はNG
- 「俺の仕事じゃない」は厳禁
むしろ、新人のころの腰の軽さ+明るさを発揮できる人が好かれます。
また、「顧問先を引き連れて独立されるかもしれない」という不安も、周囲にはあります。
数年で辞める腰掛けと思われないよう、信用の蓄積がとても重要です。
まとめ:割り切れる人にとっては最良の選択肢
私の知る限り、勤務税理士としてうまくいっている方には、以下のような共通点があります。
- 誰かと一緒に働くのが好き
- 下の人にも自然と敬意をもって接することができる
- 縁の下の力持ちを厭わない
- 安定を最優先したい
そうした方にとっては、勤務税理士という働き方はとてもフィットします。
逆に、
- 自分で仕事を設計したい
- 看板ではなく自分の名前で勝負したい
- 理念に共感できないとやる気が出ない
- やりたい仕事がある
といったタイプの方は、どこかで息苦しさを感じるかもしれません。
最後に:「自分が何を優先したいか」を見極めて
税理士としてのスキル以前に、 大切なのは「自分が何を優先したいか」という軸を持つことです。
お金なのか、自由なのか、家族との時間なのか、やりがいなのか── その答えは人それぞれです。
あなたが「自分らしい道」を選ぶための、一つの参考になれば幸いです。
次回予告
次回はいよいよ最終回: 【連載3/3】税務職員を辞めないという選択肢 ──あえて残る、というキャリアの価値を改めて見つめ直します。

記事執筆者
遠藤 光寛(えんどう みつひろ) 税理士・行政書士・FP1級
18年間の国税職員経験を経て、2018年に独立。 クラウド会計や医療法人支援を専門としながら、税務申告・記帳代行にとどまらず、人材育成・業務の仕組み化・データに基づく経営戦略立案、実行を一貫して提供している。
2020年に株式会社遠藤会計を設立し、福島県郡山市を拠点に、企業の経営基盤を支える伴走型の税理士事務所を運営。 以下のような、「現場と数字」の両面からの改善支援を強みとする。 ・債務超過企業の黒字化 ・離職率の高い組織の再構築 ・マネジメントに悩む管理職の再育成
支援の根底にあるのは、「人は財」という信念。 税務の専門家としての正確さに加え、人と組織の成長をともに考える姿勢に信頼を寄せる顧問先も多い。 すべての顧問先に税理士本人が対応し、経営者の課題に誠実に寄り添う姿勢を大切にしている。
保有資格
- 税理士
- 行政書士
- ファイナンシャル・プランニング技能士1級
- CFP®認定者
- 認定マスターコーチ
- 経営支援責任者
- 方眼ノートトレーナー
- クラウド会計ソフトfreee会計上級エキスパート
- クラウド会計ソフトfreee人事労務エキスパート
- 第二種情報処理技術者
- 初級システムアドミニストレータ
- Microsoft VBA Excel スタンダード
認定・許可
- 福島県 甲種防火管理者
- 経済産業省 経営革新等支援機関
- 厚生労働省 有料職業紹介事業所
- 福島県公安委員会 古物商許可