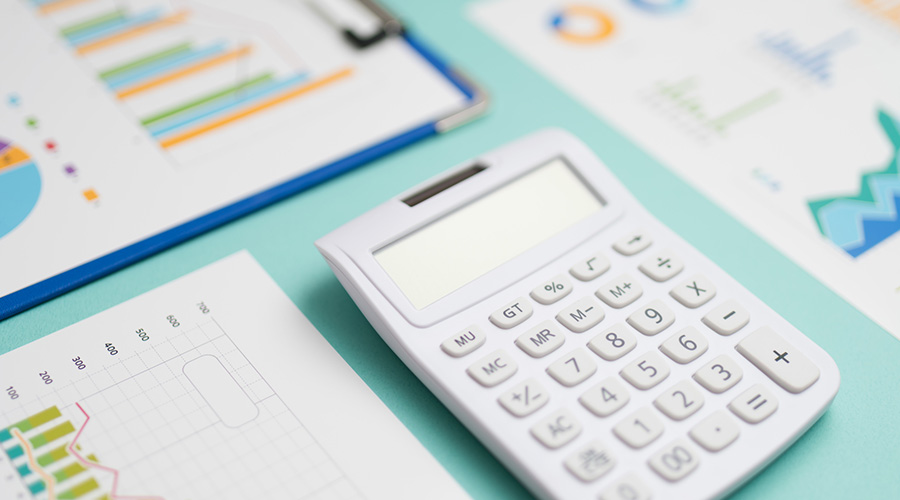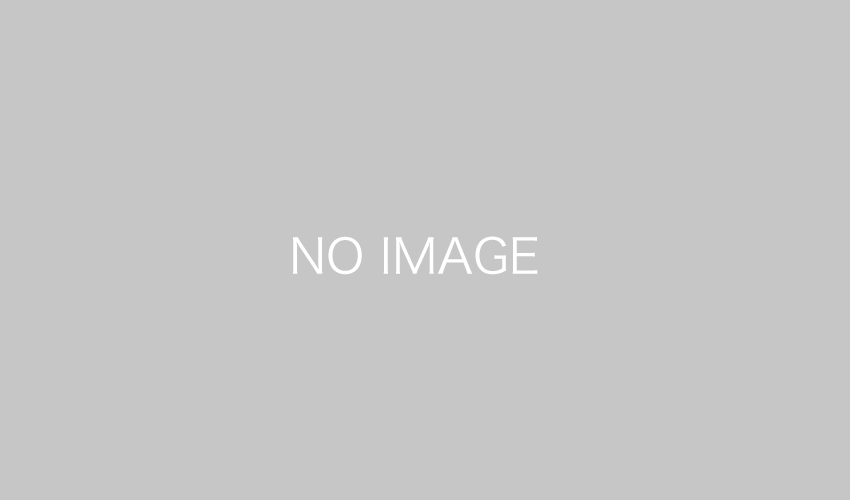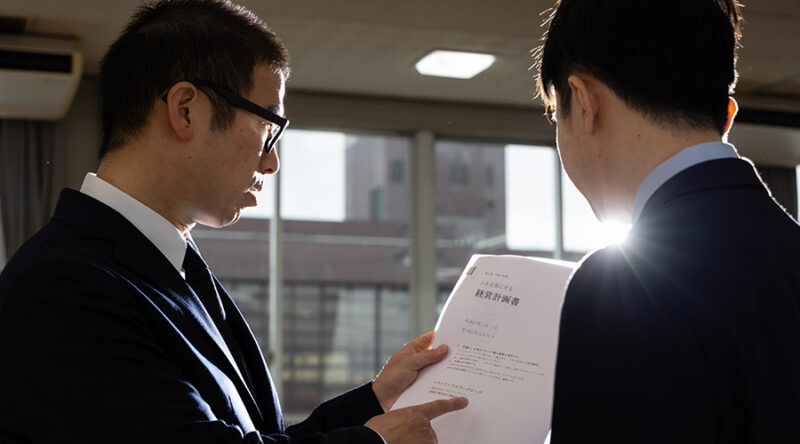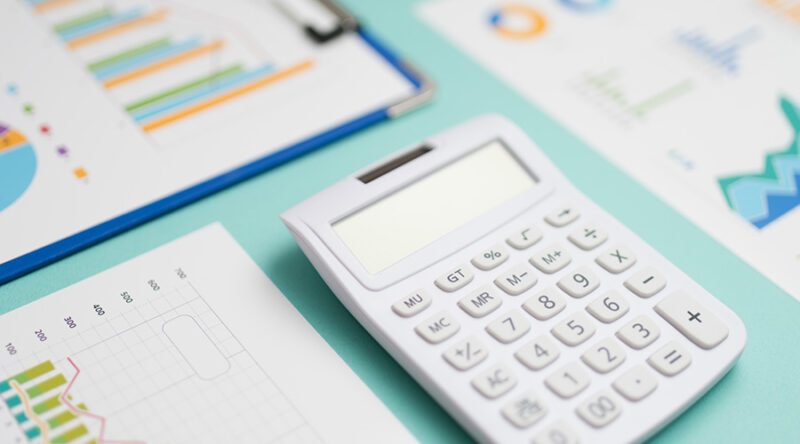【税務職員向け連載1/3】独立税理士になる前に考えてほしいこと
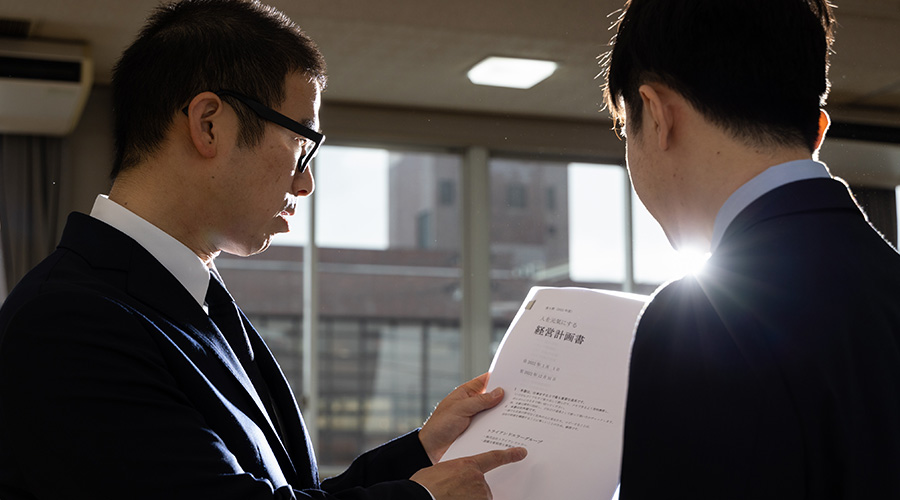
「俺は法人や資産税にいた」では食えない時代へ
こんにちは。福島県郡山市で税理士事務所を運営している、税理士の遠藤光寛です。
私は国税に18年間勤務し、現在は独立開業して7年目になります。
仙台国税局採用、期別は普通科60期になります。
この連載は、今まさに進路を迷う税務職員の方、特に
「独立するか」
「勤務税理士になるか」
「このまま役所に残るか」
を検討している方に向けて書いています。
今回は第1回、「独立税理士になる前に考えてほしいこと」。
私自身の経験と、周囲の独立事例から、現場のリアルをお伝えします。
1. 「どこにいたか」より「今、何ができるか」
私自身、国税時代の所属は個人→総務(会計)→個人→管理運営でした。
その経歴について、退職後にお会いした税務職員の方から、冗談交じりに「管理運営かぁ…」と軽い反応をいただくこともあります。
退職前は、「法人や資産税にいた人のほうが開業には有利なんだろう」と、正直コンプレックスを感じていた時期もありました。
ですが、今ならはっきり言えます。
「法人にいたかどうか」より、「いま、目の前の顧客に何ができるか」のほうが、100倍大事です。
現実の顧客ニーズは、税務署の枠をはるかに超えています。
法人税、相続税はもちろん、住民税や社保、補助金、事業再構築、業務効率化、果てはパソコンの操作方法まで聞かれます。
国税時代には「それは社保事務所に」「それは市役所に」と言えましたが、今は通用しません。
「それはうちでは扱っておりません」と言えば、それだけで信用を失う世界です。
さらに大事なのは、税理士として何ができるかです。
法人税、資産税、地方税、医療法人、社会保険、補助金、事業再構築、コンサルティングなど、勉強して、実務で使えば覚えます。チャレンジするほど習熟します。
無知ゆえに恥をかくこともあります。
けれども、その悔しさこそが、税理士としての地力と信頼を育てる原動力になるのです。
2. 得意だからこそ、弱みになる
──あなたの「専門性」、それだけで足りますか?
税務職員として、長年「法人税」「資産税」など特定の分野を専門にしてきた方も多いはずです。
・法人税は誰にも負けない
・資産税の現場なら自信がある
そう言えることは、素晴らしい実績です。経験も、知識も、豊富なのでしょう。
けれど、税理士になってから求められるのは、“専門家”ではなく“問題解決者”です。
顧客から投げかけられるのは、こんな問いです。
- 「社会保険料が高くて困っているけど、どうにかならない?」
- 「補助金、今うちが使えるのはどれ?」
- 「法人化って、そろそろした方がいいですか?」
- 「この助成金、どうやって申請すればいいの?」
- 「会計ソフト、うまく動かないんだけど?」
- 「資金繰り表ってどう作るの?」
つまり、横断的な知識と現実的な対応力が必要になります。
「法人税のことなら分かりますが、それ以外は分かりません」と言ってしまえば、
たとえ優秀でも「頼りづらい人」になってしまうのです。
実際、専門性にこだわりすぎてしまった方ほど、独立後に苦しんでいるように見えます。
専門税法は“氷山の一角”に過ぎません。
私自身も、法人税や資産税部門を経験してきた人はさぞ有利だろうと思っていた時期がありました。
でも実際には、社会保険・地方税・医療法人・年金・投資・財務・補助金──
顧客の相談に乗ろうと思えば、どれも避けては通れない分野ばかりです。
知らなかったからこそ、学びました。
学んだからこそ、顧客に頼られ、今は他の税理士事務所の研修講師として登壇できるようになりました。
これから開業する方へ伝えたいのは、
「何を得意だったか」ではなく、「これからどう学び、どう役に立つか」が大切だということです。
3. 「調査に強い」では食えない
国税出身者には「調査に強い」がウリの方が多くいらっしゃいます。
もちろん、誇るべき強みです。
これも、開業後に気づきました。
「調査に強い先生です」と言っても、調査の対象になる時点で「まずい顧客」しか持っていないことの表れ。
まずいとは、税理士が信頼されていないか、もともとそういう顧客であるということ。
(帳簿の整理が滞る、お約束が守られない、料金の支払いが滞る、他責思考など)
そのような状態の顧客を多く抱えることは、事務所運営として致命傷になることも。
ましてや、開業当初の顧客は、規模や収益の点で、そもそも調査対象にならないことも。
調査対応の出番がなく、結果的に「売り」になりません。
むしろ大事なのは、
・調査が来ない顧問先
・調査があっても何ら恥ずべきことがない顧問先
を増やすサポートができるか。
それはまさに、医師にたとえれば「天才外科医」ではなく「街のお医者さん」。
病気になってから治すのではなく、病気にならない生活習慣を整えることの方が大切なのです。
4. 「一人ですべてやる」覚悟はありますか?
開業とは、いわば「社長になること」です。
経理も営業も総務も全部、自分でやる必要があります。
申告ソフトの設定、電子申告、お客様への説明、請求書発行、営業まで──
かつて「誰かがやってくれていた」業務が、自分の肩にすべてのしかかってきます。
パソコンが苦手な人ほど、開業後のギャップに苦しみます。
特に国税では、一定のポジション以上になると、現場実務からは離れる傾向があります。
たとえるなら──
署長が、突然
・総務課職員 兼
・調査官 兼
・徴収官
になるようなもの。(上席、統括でないところがポイントです。)
どれだけ優秀であっても、「手を動かせなければ仕事にならない」のが独立の現実です。
5. 「肩書き」で選ばれない時代
・局調査課○○年
・国際税務を○○年担当していた
・審理を担当していた
・署長を歴任していた
そうした華やかな経歴は、顧客には伝わりません。
なぜなら、彼らにとって、あなたは「街の税理士」にすぎないからです。
街の税理士に大手がオファーを行うことなど、まずありません。
どんなに経験豊かであろうと、習熟していようと、街の税理士は街の税理士です。
大手は名の通っている事務所、大所帯の事務所にオファーします。
経験でもスキルでもなく、仕事の大きさは事務所の看板に比例するのです。
申告書の税理士署名を見るたび、「なんでこの会社がこの事務所(先生)に?」と首を傾げた税務職員の方も多いかと思います。
これが世間と税務職員の情報ギャップです。
つまり、世間の評価は、看板の大きさで決まるということです。
名前の知れた事務所は実態はともかく「良い事務所、立派な事務所」と評価され大きな仕事や量が多く舞い込みますが、無名の事務所は「大丈夫?やっぱやめておこう…」と評価されてしまいます。
結果、業界からすると本当に品質の良い事務所(先生)は表に出ることなく、ひっそりやっているのが現実です。
これをきっと、痛烈に感じることになります。
国税の看板が外れた瞬間、あなたは「ゼロスタート」です。
評価はコツコツ積み上げていくしかありません。
選ばれるのは、顧客から「この人なら、いまの悩みを解決してくれる」と感じた人です。
その場で、寄り添って、対応できる力。
過去ではなく、今です。
6. 減点評価から加点評価へ
ある程度の年数、組織に身を置いてきた方なら、体感として分かるでしょう。
組織の中では、「成果を出す人」よりも「失敗しない人」のほうが高く評価されがちです。
つまり、派手な活躍よりも、波風を立てず、決められた仕事を淡々とこなす人のほうが、出世しやすい構造があるのです。
一方で、挑戦を恐れず、新しい価値を生み出すような人
──たとえば、成果も大きいけれど失敗もあるような「サラリーマン金太郎」型の職員は、往々にして組織の“中央”からは外されていきます。
しかし、独立するとその評価軸は180度ひっくり返ります。
失敗を恐れて動かない人、前年通りを繰り返し、無難に任期を終えようとする人。
──そうした姿勢は、経営者からすれば評価の対象にはなりません。
むしろ「何のために報酬を払うのか」と疑問を持たれる存在になってしまいます。
反対に、多少の失敗があっても、しっかりと成果を残す人。
新しい価値を生み出し、顧客に「頼れる」と思わせられる人。
そうした人材こそが評価され、選ばれていくのです。
だからこそ、組織の中で「お上品に」歩んできた人ほど、独立後に存在感を発揮しづらく、静かに市場から退いていくことが少なくありません。
自分の価値がどこで、どのように評価されるのか──
環境が変われば、その物差しも大きく変わるのです。
7. 組織のありがたみは、辞めてから分かる
毎月の安定収入、賞与、有給休暇、共済組合、部門の役割分担。
さらには、働く場所、車、デスク、PC、会計ソフト、消耗品(コピー用紙)に至るまで―
開業すれば、それらはすべて「自分で用意するもの」になります。
それらは決して無料ではありません。
ミスプリント1枚でも、お金が消えていくのです。
さらには、税理士でいるためには会費の支払いが必要になります。
税理士本会、県会費、支部会費、などなど資格を維持するためには欠かせません。
当然、収入(お客様)がなくては、これらを賄うこともできません。
家族がいる方にとっては、相当な覚悟が必要です。
武士は食わねど高楊枝ではありません。
精神的にも肉体的にも、独立とは「孤独との戦い」でもあります。
最後に:それでも「やりたい」なら、覚悟を持って
私は、国税時代一緒した方からよくこう聞かれます。
「開業して、よかったですか?」
その答えは──
「覚悟を決めたなら、これ以上に自由で面白い仕事はない」
ということです。
ただし、それは「覚悟を決めたら」の話。
独立は、万能薬でも、逃げ道でもありません。
地に足をつけて、準備を整えてから踏み出してください。
あなたの選択が、人生のターニングポイントになることを心から願っています。
今回は、独立開業という選択肢について、実体験を交えながらお伝えしました。
次回は、
【連載2/3】「勤務税理士になる前に考えてほしいこと」
──安定を選ぶという決断の裏側にある、もうひとつの現実についてお話しします。

記事執筆者
遠藤 光寛(えんどう みつひろ)
税理士・行政書士・FP1級
18年間の国税職員経験を経て、2018年に独立。
クラウド会計や医療法人支援を専門としながら、税務申告・記帳代行にとどまらず、人材育成・業務の仕組み化・データに基づく経営戦略立案、実行を一貫して提供している。
2020年に株式会社遠藤会計を設立し、福島県郡山市を拠点に、企業の経営基盤を支える伴走型の税理士事務所を運営。
以下のような、「現場と数字」の両面からの改善支援を強みとする。
・債務超過企業の黒字化
・離職率の高い組織の再構築
・マネジメントに悩む管理職の再育成
支援の根底にあるのは、「人は財」という信念。
税務の専門家としての正確さに加え、人と組織の成長をともに考える姿勢に信頼を寄せる顧問先も多い。
すべての顧問先に税理士本人が対応し、経営者の課題に誠実に寄り添う姿勢を大切にしている。
保有資格
- 税理士
- 行政書士
- ファイナンシャル・プランニング技能士1級
- CFP®認定者
- 認定マスターコーチ
- 経営支援責任者
- 方眼ノートトレーナー
- クラウド会計ソフトfreee会計上級エキスパート
- クラウド会計ソフトfreee人事労務エキスパート
- 第二種情報処理技術者
- 初級システムアドミニストレータ
- Microsoft VBA Excel スタンダード
認定・許可
- 福島県 甲種防火管理者
- 経済産業省 経営革新等支援機関
- 厚生労働省 有料職業紹介事業所
- 福島県公安委員会 古物商許可